私の記憶に残る4人のストライカーの個性
ゴール(得点)というものはどんなレベルのサッカーでも重大なものだ。
ときに、それは、ペナルティーエリアに至るまでの輝かしいプレーの集積でもあり
ときには、個人プレーの所産でもある。
混戦から生まれることも、オウン・ゴールも
PKのゴールもあるが、すべてが1点となる。
ゴールは、得点者にも、それを見る人々にも新たな感動の波を呼び起こし
多くの人を喜ばせ、また、多くの人を失望させるのだ。
(デニス・ロー)
1964年の欧州フットボーラー・オブ・ザ・イヤーだったデニス・ロー(スコットランド、マンチェスター・ユナイテッド)は、「記憶に残るゴール」という──書き物の中でこんな風に言っている。
リードされていても、していても、1点がどれだけ仲間の士気を高めるかは、誰もが経験することだ。校庭でプレーする少年達にも、マラドーナやルムメニゲのような高給取りのプロフェッショナルにも「ゴール」は共通の感情で、また子供を応援する父兄にとっても、クラブのサポーターにも、そして国際試合やワールドカップをテレビで見る世界中のファンに、共通なものだと思う。
こうした得点を生み出すのは、あくまでチームプレーによる──試合中のプレーにはすべて、それ以前の「流れ」があり、ロングシュートの得点でも、単身突破でも、仲間の働きと無縁で成り立ちはしない──が、攻撃のフィニッシュを担当するストライカーのポジションプレーもまた重要な役割を占めることになる。
ストライカーの技術、戦術を分析し、その練習法などについて、皆さんと勉強していく前に、まず、私の記憶に残るゴールを幾つか取り上げてみたい。それによって、それらの得点の成功を生んだストライカーの個性や技術を眺めてみよう。
ペレ=左右、前後。それに横の動きが伴う!
1952年(昭和47年)5月26日
東京・国立競技場での日本代表−FCサントス(ブラジル)でのペレの2ゴール
サントスを率いて、初めて日本にやってきたエドソン・アランテス・ド・ナシメント。「ペレ」は、31歳。1970年のワールドカップ優勝の後、ナショナルチームから引退していたが、この試合では2つのゴールを決め、“王様”健在を印象づけた。両方とも、ボールを浮かせて密着マーク(山口選手)を外してのシュートだが、とくに2点目(チームの3点目)は山口をかわし、ついで第2のDF(小城選手)をも、ボールを浮かせて逆をとり、バウンドしたボールを頭で突いて出て、小城を振り切り、左足のボレーシュートをゴール左上隅に決めるという“神技”。ペレ自身も最高のゴールと言っていた。
ボールを浮かせて相手DFをかわすのは、ペレの得意ワザの一つ。1958年、彼が17歳でワールドカップ(スウェーデン大会)にデビューしたとき、ファイナルゲームでスウェーデンのDF2人を、次々にかわして、ボレーシュートを決めたビューティフル・ゴールは彼を世界のスターにしたものだ。このときは、太股のトラッピングで、まず一人をかわして左へすり抜け、ついで2人目の頭を越して背後に回り込んだが、東京の2点目は、
(1)まず、後ろを向いて高いロブを胸でトラップ。このとき、ジャンプして、ボールを取ろうとした山口を背中でカバーしながら反転して前(相手ゴール)へ向き直り
(2)ボールが地面に落ちるまでに、足の甲で左前へ浮かして(山口の後方で狙っていた)小城を左へかわし
(3)次いで、頭で、突いて出したのだった。
ちょうど2分前にペレの1点目が生まれていた。後方からのパスを、足でボールを左手前へ浮かせ、背後の山口と競り合いながら、左へターン(ゴールに向かって右側へ流れる)、山口を腕で押さえつつ、右足のボレーシュートを決めている。いわば、浮きダマを使って右横へ外し、(抜き切らずに)次のDFが出てくるまでにシュートをしたものだったが、2点目は二人目の相手を外す、つまり、シュートのタイミングを(最初に山口と体を入れ替えてから)2度もずらせて成功させたところが誰もマネのできないペレらしさがある。
彼の非凡さは、まず右(利き足)でも左でもシュートが利くこと。そしてまた、右回りも左回りもスムーズであること──という、もっとも基礎的なものから始まっている。天性のバネと、体の柔らかさが、こうした複数のタイミングを可能にし、また、試合の流れと、相手の心理まで読む鋭いカンが、彼の幾つもの技術パターンを、ときに応じて使い分け、相手を惑わし、得点を生み出してきたのだった。
ミュラー=粘着力と反転のストライカー
1974年7月7日
西ドイツのミュンヘン、オリンピックスタジアムでの1974年ワールドカップ決勝
ゲルト・ミュラーの決勝ゴール
オランダが開始直後のPKでリードし、西ドイツが25分にやはりPKで同点、1−1で進んだゲームは43分に西ドイツが2点目を挙げる。決めたのは西ドイツのCF(センターフォワード)ゲルト・ミュラー。このゴールが結局、決勝点となって西ドイツが2度目のワールドカップ優勝に輝いた。
この得点のための攻撃は、まず、防御のために自陣ペナルティーエリアまでニースケンス(オランダ)を追ったMFのボンホフから始まる。ボールを奪ったボンホフがGKマイヤーに渡す。マイヤーは、すぐ右へ開いたDFのシュバルツェンベックへボールを送った。
さあ反撃という形になって、シュバルツェンベックは中央線付近のグラボウスキーへ。いっせいに後退してマークを固めたオランダ側を誘うように、ドリブルの名手グラボウスキーは右タッチラインへ、するするとドリブルで上がっていった。
そのとき、後方からボンホフが駆け上がってくる。グラボウスキーからパスを受けたボンホフは、オランダのハーンの追走を振り切りペナルティーエリアに侵入。タックルに来たレイスベルヘンをタテにかわして中央へパス。
このパスを受けたゲルト・ミュラーは右足のアウトサイドで、いったんボールを後方へ置き、後ろへ戻って、振り向きざまに右足でシュート。ボールはタックルしようとしたクロルの足の下を抜け、GKヨングブルートの左側(GKから見れば右手側)を通ってゴールに入った。
この得点経路では、もちろん、一人ひとりのボールの受け方、パスの出し方、その方向、タイミングなど、いずれも大切だが、なかでも、ボンホフの長い疾走と、それに続くドリブルとパス、そしてシュートをしたミュラーの特技が、重要なポイントだと思う。
ゲルト・ミュラーは1970年ワールドカップの得点王(10点=6試合)。ブンデスリーガでは1971−72では40得点(34試合)1972−73で36得点(33試合)の高得点をマークしている。彼は相手のマーク役を背にしてボールを受け、反転してシュートへ持っていく特異な才能を持っていた。足の踏み変えで、体の下にあるボールでも、すぐにシュート体勢に入ったし、ボールを左右に動かして、腰のひねりを利かしてのシュートも彼の、持ち芸だった。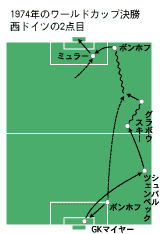
ボンホフの突進で、オランダDFのマークがずれて、ストッパーであるレイスベルヘンがボンホフの方へ出ていき、その後のマークはクロルが引き継いでいた。そのクロルの位置を睨みながら、ミュラーは右足アウトサイド(カカトに近い)でボールを体の後方に残した。意識的に置いたのか、あるいは止め損なったのか、いずれにしても普通のプレーヤーなら、すぐシュートの体勢にはなれないところにボールはあったが、ミュラーは、後方に戻るなり右足でシュートした。GKヨングブルートにはミュラーが蹴った瞬間はブラインドとなって見えなかったに違いない。彼の体が反応したときには、ボールはゴールラインに来ていた。
ゲルト・ミュラーは、1メートル75、77キロ、CFとしては、上背がない方で、ずんぐりむっくり型。重心が低く安定し、反転が早く、ために相手を背に(ゴールを背に)しても自信満々。ペナルティーエリア内では(相手もひどい反則はできないから)足下にボールを受けて、平気で持ちこたえ、味方にパスも出すし、ターンしてのシュートもする。バイエルン・ミュンヘンでは、ミュラーとベッケンバウアーのカベパスが一つの決め手になっていたのも、ベッケンバウアーに戻してシュートさせ、あるいは自分でターンしてシュートするのか、どちらをも相手は予測しにくいからだった。そのターンが、右回りでも、左回りでも自在で、(右はもちろん)左足のシュートもできる。そして、そのターンの最中に止まるとみせて、動く、いわば、ストップ・アンド・ゴーがあって、相手はタックルのタイミングを計るのに困惑する。
自分のシュートの型を土台に攻撃を組み立て、フィニッシュへ持っていくプレーとは別に、ゴール前でのリバウンドや、一つのプレーの後で、ボールがどこに来るか、を察知する能力と、その位置どりの良さも格別だった。1974年、2次リーグの対ユーゴ戦でヘーネスの右からグラウンダーに併せて走りこみ、相手DFと倒れながら、転倒直後に右足で、一瞬早くボールにタッチして決めた得点。1970年ワールドカップ対イングランド戦の3点目のボレーシュートなどは、彼の位置どりのうまさと、ボールに対する反応の早さの成果だろう。
ケンペス=爆走するストライカー!
1978年6月25日
ブエノスアイレス、リバープレートでのワールドカップ決勝 アルゼンチン3−1オランダ
前半38分、アルゼンチンのゴール
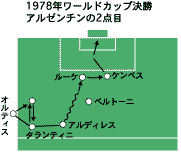 1974年2位のオランダがクライフ抜きながら豊富な運動量とロングシュートで勝ち残り、2次リーグから攻撃が軌道に乗った開催国アルゼンチンとの決戦。アルゼンチンはアルディス、ルーケ、ケンペスのトリオの働きでまず先制した。
1974年2位のオランダがクライフ抜きながら豊富な運動量とロングシュートで勝ち残り、2次リーグから攻撃が軌道に乗った開催国アルゼンチンとの決戦。アルゼンチンはアルディス、ルーケ、ケンペスのトリオの働きでまず先制した。
図にあるとおり、これは、左サイドのスローインから始まり、投げたオルティスと、受けたタランティニの間でボールのやりとりがある。ゆっくりした、このパスの間にオランダのケルクホフがタランティニに詰める。そのケルクホフの足のぎりぎりのところでタランティニはアルディレスに(ハーフラインに平行の)パスを送る。
この短いパスを受けたアルディレスは、独特のオートバイのスタートのような早さで、2人のオランダ選手の間を通りすぎ、ペナルティーエリア近くのルーケに渡す。ルーケはパスを受けるなり、右足で突っつくようにして走りこんできたケンペスへ。ケンペスは左斜め前へ突進し、併走するハーンが足を出す前に、左足でスライディングシュート。飛び出してきたGKヨングブルートの左手側をボールはゆっくり転がってゴールインした。
マリオ・アルベルト・ケンペスはこのとき満24歳に20日ほど(誕生日は7月15日)欠けていた。左利きで、少年の頃から強いシュートをすることで知られていたマリオは1974年ワールドカップにアルゼンチン代表として参加した後、スペインのバレンシアに移り、スペイン・リーグの得点王になった。この大会の直前にメノッティが呼び戻すことのできた唯一の外国クラブ籍の選手だった。
彼は、この決勝の延長でも30メートルドリブルで突進し勝ち越しゴールを決め、大会を通じて6得点。記者投票で優秀選手に選ばれ、得点王も獲得。
彼の特色は、後方からスピードに乗っての攻め上がりにある。助走をし、パスを受け、スピードに乗れば、そのドリブルは無敵となる。1次リーグでは、もっぱら第一線ににいたから、彼のこの特徴は生きずイタリア戦ではCFのポジションでイタリアの厚い守りに包まれてしまった。2次リーグに入って、第2列に下がってから、その特色が発揮されたが、彼の左足のシュートで自信のある角度はほぼ決まっていた。そのためにシュートの位置は左ポストの延長線が良く、最終DFをかわすときに、左へ流れた方が有効だった。 この決勝の1点目は、いわば彼の最も得意の形といえる。
左へ流れながらであれば、高速でも、また相手に妨害されてもくじけずシュートできる強さを持っていた。
彼はこの確率の高いシュートのコースを生かすために仲間の協力が必要だったが、この大会ではCFルーケの動きが効果があった。ルーケは、トップとして前方に残っていて、すばやく自分の位置をずらせて、ケンペスの進入路をあけてやった。ルーケは反転シュートがいいので、彼をマークする相手DFはペナルティーエリア付近で彼が動けば、放っておくわけにいかない(放っておくとシュートされる)。そこでルーケが移動すると、そのあとにスペースが生まれるのだった。
1978年のアルゼンチンが、狭い地域の攻撃を繰り返しながら、得点できたのは、彼らの得点ワザの組み合わせと、タイミング、そして狭い地域でも通用する精密なボールタッチとスピードがあったからだ。
ケンペスと同じアルゼンチン生まれで、左足のマラドーナとを、ここで比べてみよう。
マラドーナもすべて左足で処理するが、彼は、右へ流れたときでも(ゴールの右ポストより、なお右へ寄っても)ゴールへのシュートの角度を持っている。ペナルティーエリア右角からのFKは彼の得意のコースだし、右サイドから、この位置へ侵入してきてのシュートも決めているし、また、左から右へ斜行した後でも態勢を立て直してシュートに入ってくる。もちろん、左利きシューターの得意の左斜めへ出たときは自信を持っている。同じサウスポーでも小さなマラドーナの方がゴールへ攻めこむコースが多く、大柄なケンペスの方がコースが限定されている。
78年のワールドカップで24歳だったケンペスに、82年ワールドカップの活躍を期待した人も多かったハズだ。
しかし、彼は別人のようだった。足の故障でコンディショニングの失敗があったかも知れない。相手チームもケンペスの特色を研究したこともあるだろう。しかし、私は、78年のように彼の特性を引き出すような個性の組み合わせはなかったと思っている。彼の高速突進のなかでの精妙な左足のボールタッチと、エキサイティングなゴールは78年大会だけに終わったのは本当に惜しい。
ロッシ=消える「おとなしの」ストライカー
1982年7月11日 マドリッドのサンチャゴ・ベルナベウ
ワールドカップ決勝 イタリア−西ドイツ
後半11分、イタリアの先制ゴール
前半0−0、後半11分、西ドイツ側の反則で、イタリアはドイツ陣25メートルでFK。ドイツ側がまだ守備体制に入らない内に、右サイドへ、ジェンチーレが上がって来た。それを見て、タルデリがFKを右へ振る。ノーマークのジェンチーレは、右サイドから、まるでここからFKとでもいうように狙って、ゴール前へライナークロスを送った。これに合わせて飛び込んだのが左DFのカブリーニ、バウンドしたボールにカブリーニは合わなかったが、その左側にパオロ・ロッシがいた。姿勢を低くし、頭に当てたボールは、ゴール左へ。
1982年ワールドカップでイタリア優勝の立役者となったパオロ・ロッシ(1メートル78、76キロ)については皆さんもまだ記憶に新しいハズだ。私には、1978年のワールドカップと今度のワールドカップしか見るチャンスのなかったプレーヤー(出場停止処分のため1980年欧州選手権も、コパデオロも出ていないから)で、彼のオリジナルがどこにあるかは、はっきりしていない。ただし、はっきりしているのは、ゴール前の、相手の一番イヤなところへ、入り込んで、ボールを受けることの上手いこと。そして、攻撃開始のときに絡むドリブルの方向のいいこと。
82年のワールドカップ2次リーグでブラジルから奪った3得点は、一つは、左からのクロスをファーポストでヘディングし、一つは、相手バックスの横パスをかっさらってのシュート。もう一つはCKの後の味方のシュートをゴールマウスで足に当てたものだった。
頑健型でなく、スリムで、早さを基調とするロッシは、78年ワールドカップの19歳の頃に、すでに、“速”の中に“遅”、急のなかに緩を織り込むことを知っていた。プロフェッショナルともなれば、まず「急」がなければならぬが、急だけで相手を困惑させる力がある若い内に、緩を身に付けるのも一つの大きな才能だ。
緩と急の他に、ロッシは、もう一つ相手の守りのイヤな地域に気付かれずに侵入する才能を持っている。
日本ではベルリン・オリンピック(1936年)以来、長くシュートの名人と言われた川本泰三さんが、“消える”名人であった。相手の視野から消え、ゴール前の危険地帯に気付かれずに入って来る訳だが、ロッシもこの“消える”要領を知っているようだ。私の記憶では62年ワールドカップのソ連のCFワレンチン・イワノフとも似たところがある。
王様ペレが日本で見せたスーパーゴール、そして、皆さんもテレビでご存知の74年、78年、82年ワールドカップ決勝の得点シーンを思い出し、そのゴールスコアラーとなったストライカーの個性を比べてみた。
次項から、日本が生んだ釜本邦茂選手(現・ヤンマー監督)の幾つかのゴールシーンを再現し、そのときにどのような技術や、戦術が必要だったかを勉強したいと思う。
(サッカーマガジン 1983年11月1日号)
ときに、それは、ペナルティーエリアに至るまでの輝かしいプレーの集積でもあり
ときには、個人プレーの所産でもある。
混戦から生まれることも、オウン・ゴールも
PKのゴールもあるが、すべてが1点となる。
ゴールは、得点者にも、それを見る人々にも新たな感動の波を呼び起こし
多くの人を喜ばせ、また、多くの人を失望させるのだ。
(デニス・ロー)
1964年の欧州フットボーラー・オブ・ザ・イヤーだったデニス・ロー(スコットランド、マンチェスター・ユナイテッド)は、「記憶に残るゴール」という──書き物の中でこんな風に言っている。
リードされていても、していても、1点がどれだけ仲間の士気を高めるかは、誰もが経験することだ。校庭でプレーする少年達にも、マラドーナやルムメニゲのような高給取りのプロフェッショナルにも「ゴール」は共通の感情で、また子供を応援する父兄にとっても、クラブのサポーターにも、そして国際試合やワールドカップをテレビで見る世界中のファンに、共通なものだと思う。
こうした得点を生み出すのは、あくまでチームプレーによる──試合中のプレーにはすべて、それ以前の「流れ」があり、ロングシュートの得点でも、単身突破でも、仲間の働きと無縁で成り立ちはしない──が、攻撃のフィニッシュを担当するストライカーのポジションプレーもまた重要な役割を占めることになる。
ストライカーの技術、戦術を分析し、その練習法などについて、皆さんと勉強していく前に、まず、私の記憶に残るゴールを幾つか取り上げてみたい。それによって、それらの得点の成功を生んだストライカーの個性や技術を眺めてみよう。
ペレ=左右、前後。それに横の動きが伴う!
1952年(昭和47年)5月26日
東京・国立競技場での日本代表−FCサントス(ブラジル)でのペレの2ゴール
サントスを率いて、初めて日本にやってきたエドソン・アランテス・ド・ナシメント。「ペレ」は、31歳。1970年のワールドカップ優勝の後、ナショナルチームから引退していたが、この試合では2つのゴールを決め、“王様”健在を印象づけた。両方とも、ボールを浮かせて密着マーク(山口選手)を外してのシュートだが、とくに2点目(チームの3点目)は山口をかわし、ついで第2のDF(小城選手)をも、ボールを浮かせて逆をとり、バウンドしたボールを頭で突いて出て、小城を振り切り、左足のボレーシュートをゴール左上隅に決めるという“神技”。ペレ自身も最高のゴールと言っていた。
ボールを浮かせて相手DFをかわすのは、ペレの得意ワザの一つ。1958年、彼が17歳でワールドカップ(スウェーデン大会)にデビューしたとき、ファイナルゲームでスウェーデンのDF2人を、次々にかわして、ボレーシュートを決めたビューティフル・ゴールは彼を世界のスターにしたものだ。このときは、太股のトラッピングで、まず一人をかわして左へすり抜け、ついで2人目の頭を越して背後に回り込んだが、東京の2点目は、
(1)まず、後ろを向いて高いロブを胸でトラップ。このとき、ジャンプして、ボールを取ろうとした山口を背中でカバーしながら反転して前(相手ゴール)へ向き直り
(2)ボールが地面に落ちるまでに、足の甲で左前へ浮かして(山口の後方で狙っていた)小城を左へかわし
(3)次いで、頭で、突いて出したのだった。
ちょうど2分前にペレの1点目が生まれていた。後方からのパスを、足でボールを左手前へ浮かせ、背後の山口と競り合いながら、左へターン(ゴールに向かって右側へ流れる)、山口を腕で押さえつつ、右足のボレーシュートを決めている。いわば、浮きダマを使って右横へ外し、(抜き切らずに)次のDFが出てくるまでにシュートをしたものだったが、2点目は二人目の相手を外す、つまり、シュートのタイミングを(最初に山口と体を入れ替えてから)2度もずらせて成功させたところが誰もマネのできないペレらしさがある。
彼の非凡さは、まず右(利き足)でも左でもシュートが利くこと。そしてまた、右回りも左回りもスムーズであること──という、もっとも基礎的なものから始まっている。天性のバネと、体の柔らかさが、こうした複数のタイミングを可能にし、また、試合の流れと、相手の心理まで読む鋭いカンが、彼の幾つもの技術パターンを、ときに応じて使い分け、相手を惑わし、得点を生み出してきたのだった。
ミュラー=粘着力と反転のストライカー
1974年7月7日
西ドイツのミュンヘン、オリンピックスタジアムでの1974年ワールドカップ決勝
ゲルト・ミュラーの決勝ゴール
オランダが開始直後のPKでリードし、西ドイツが25分にやはりPKで同点、1−1で進んだゲームは43分に西ドイツが2点目を挙げる。決めたのは西ドイツのCF(センターフォワード)ゲルト・ミュラー。このゴールが結局、決勝点となって西ドイツが2度目のワールドカップ優勝に輝いた。
この得点のための攻撃は、まず、防御のために自陣ペナルティーエリアまでニースケンス(オランダ)を追ったMFのボンホフから始まる。ボールを奪ったボンホフがGKマイヤーに渡す。マイヤーは、すぐ右へ開いたDFのシュバルツェンベックへボールを送った。
さあ反撃という形になって、シュバルツェンベックは中央線付近のグラボウスキーへ。いっせいに後退してマークを固めたオランダ側を誘うように、ドリブルの名手グラボウスキーは右タッチラインへ、するするとドリブルで上がっていった。
そのとき、後方からボンホフが駆け上がってくる。グラボウスキーからパスを受けたボンホフは、オランダのハーンの追走を振り切りペナルティーエリアに侵入。タックルに来たレイスベルヘンをタテにかわして中央へパス。
このパスを受けたゲルト・ミュラーは右足のアウトサイドで、いったんボールを後方へ置き、後ろへ戻って、振り向きざまに右足でシュート。ボールはタックルしようとしたクロルの足の下を抜け、GKヨングブルートの左側(GKから見れば右手側)を通ってゴールに入った。
この得点経路では、もちろん、一人ひとりのボールの受け方、パスの出し方、その方向、タイミングなど、いずれも大切だが、なかでも、ボンホフの長い疾走と、それに続くドリブルとパス、そしてシュートをしたミュラーの特技が、重要なポイントだと思う。
ゲルト・ミュラーは1970年ワールドカップの得点王(10点=6試合)。ブンデスリーガでは1971−72では40得点(34試合)1972−73で36得点(33試合)の高得点をマークしている。彼は相手のマーク役を背にしてボールを受け、反転してシュートへ持っていく特異な才能を持っていた。足の踏み変えで、体の下にあるボールでも、すぐにシュート体勢に入ったし、ボールを左右に動かして、腰のひねりを利かしてのシュートも彼の、持ち芸だった。
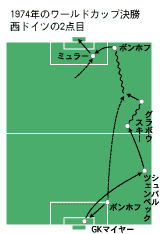
ボンホフの突進で、オランダDFのマークがずれて、ストッパーであるレイスベルヘンがボンホフの方へ出ていき、その後のマークはクロルが引き継いでいた。そのクロルの位置を睨みながら、ミュラーは右足アウトサイド(カカトに近い)でボールを体の後方に残した。意識的に置いたのか、あるいは止め損なったのか、いずれにしても普通のプレーヤーなら、すぐシュートの体勢にはなれないところにボールはあったが、ミュラーは、後方に戻るなり右足でシュートした。GKヨングブルートにはミュラーが蹴った瞬間はブラインドとなって見えなかったに違いない。彼の体が反応したときには、ボールはゴールラインに来ていた。
ゲルト・ミュラーは、1メートル75、77キロ、CFとしては、上背がない方で、ずんぐりむっくり型。重心が低く安定し、反転が早く、ために相手を背に(ゴールを背に)しても自信満々。ペナルティーエリア内では(相手もひどい反則はできないから)足下にボールを受けて、平気で持ちこたえ、味方にパスも出すし、ターンしてのシュートもする。バイエルン・ミュンヘンでは、ミュラーとベッケンバウアーのカベパスが一つの決め手になっていたのも、ベッケンバウアーに戻してシュートさせ、あるいは自分でターンしてシュートするのか、どちらをも相手は予測しにくいからだった。そのターンが、右回りでも、左回りでも自在で、(右はもちろん)左足のシュートもできる。そして、そのターンの最中に止まるとみせて、動く、いわば、ストップ・アンド・ゴーがあって、相手はタックルのタイミングを計るのに困惑する。
自分のシュートの型を土台に攻撃を組み立て、フィニッシュへ持っていくプレーとは別に、ゴール前でのリバウンドや、一つのプレーの後で、ボールがどこに来るか、を察知する能力と、その位置どりの良さも格別だった。1974年、2次リーグの対ユーゴ戦でヘーネスの右からグラウンダーに併せて走りこみ、相手DFと倒れながら、転倒直後に右足で、一瞬早くボールにタッチして決めた得点。1970年ワールドカップ対イングランド戦の3点目のボレーシュートなどは、彼の位置どりのうまさと、ボールに対する反応の早さの成果だろう。
ケンペス=爆走するストライカー!
1978年6月25日
ブエノスアイレス、リバープレートでのワールドカップ決勝 アルゼンチン3−1オランダ
前半38分、アルゼンチンのゴール
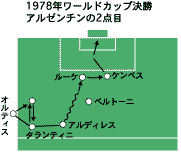 1974年2位のオランダがクライフ抜きながら豊富な運動量とロングシュートで勝ち残り、2次リーグから攻撃が軌道に乗った開催国アルゼンチンとの決戦。アルゼンチンはアルディス、ルーケ、ケンペスのトリオの働きでまず先制した。
1974年2位のオランダがクライフ抜きながら豊富な運動量とロングシュートで勝ち残り、2次リーグから攻撃が軌道に乗った開催国アルゼンチンとの決戦。アルゼンチンはアルディス、ルーケ、ケンペスのトリオの働きでまず先制した。図にあるとおり、これは、左サイドのスローインから始まり、投げたオルティスと、受けたタランティニの間でボールのやりとりがある。ゆっくりした、このパスの間にオランダのケルクホフがタランティニに詰める。そのケルクホフの足のぎりぎりのところでタランティニはアルディレスに(ハーフラインに平行の)パスを送る。
この短いパスを受けたアルディレスは、独特のオートバイのスタートのような早さで、2人のオランダ選手の間を通りすぎ、ペナルティーエリア近くのルーケに渡す。ルーケはパスを受けるなり、右足で突っつくようにして走りこんできたケンペスへ。ケンペスは左斜め前へ突進し、併走するハーンが足を出す前に、左足でスライディングシュート。飛び出してきたGKヨングブルートの左手側をボールはゆっくり転がってゴールインした。
マリオ・アルベルト・ケンペスはこのとき満24歳に20日ほど(誕生日は7月15日)欠けていた。左利きで、少年の頃から強いシュートをすることで知られていたマリオは1974年ワールドカップにアルゼンチン代表として参加した後、スペインのバレンシアに移り、スペイン・リーグの得点王になった。この大会の直前にメノッティが呼び戻すことのできた唯一の外国クラブ籍の選手だった。
彼は、この決勝の延長でも30メートルドリブルで突進し勝ち越しゴールを決め、大会を通じて6得点。記者投票で優秀選手に選ばれ、得点王も獲得。
彼の特色は、後方からスピードに乗っての攻め上がりにある。助走をし、パスを受け、スピードに乗れば、そのドリブルは無敵となる。1次リーグでは、もっぱら第一線ににいたから、彼のこの特徴は生きずイタリア戦ではCFのポジションでイタリアの厚い守りに包まれてしまった。2次リーグに入って、第2列に下がってから、その特色が発揮されたが、彼の左足のシュートで自信のある角度はほぼ決まっていた。そのためにシュートの位置は左ポストの延長線が良く、最終DFをかわすときに、左へ流れた方が有効だった。 この決勝の1点目は、いわば彼の最も得意の形といえる。
左へ流れながらであれば、高速でも、また相手に妨害されてもくじけずシュートできる強さを持っていた。
彼はこの確率の高いシュートのコースを生かすために仲間の協力が必要だったが、この大会ではCFルーケの動きが効果があった。ルーケは、トップとして前方に残っていて、すばやく自分の位置をずらせて、ケンペスの進入路をあけてやった。ルーケは反転シュートがいいので、彼をマークする相手DFはペナルティーエリア付近で彼が動けば、放っておくわけにいかない(放っておくとシュートされる)。そこでルーケが移動すると、そのあとにスペースが生まれるのだった。
1978年のアルゼンチンが、狭い地域の攻撃を繰り返しながら、得点できたのは、彼らの得点ワザの組み合わせと、タイミング、そして狭い地域でも通用する精密なボールタッチとスピードがあったからだ。
ケンペスと同じアルゼンチン生まれで、左足のマラドーナとを、ここで比べてみよう。
マラドーナもすべて左足で処理するが、彼は、右へ流れたときでも(ゴールの右ポストより、なお右へ寄っても)ゴールへのシュートの角度を持っている。ペナルティーエリア右角からのFKは彼の得意のコースだし、右サイドから、この位置へ侵入してきてのシュートも決めているし、また、左から右へ斜行した後でも態勢を立て直してシュートに入ってくる。もちろん、左利きシューターの得意の左斜めへ出たときは自信を持っている。同じサウスポーでも小さなマラドーナの方がゴールへ攻めこむコースが多く、大柄なケンペスの方がコースが限定されている。
78年のワールドカップで24歳だったケンペスに、82年ワールドカップの活躍を期待した人も多かったハズだ。
しかし、彼は別人のようだった。足の故障でコンディショニングの失敗があったかも知れない。相手チームもケンペスの特色を研究したこともあるだろう。しかし、私は、78年のように彼の特性を引き出すような個性の組み合わせはなかったと思っている。彼の高速突進のなかでの精妙な左足のボールタッチと、エキサイティングなゴールは78年大会だけに終わったのは本当に惜しい。
ロッシ=消える「おとなしの」ストライカー
1982年7月11日 マドリッドのサンチャゴ・ベルナベウ
ワールドカップ決勝 イタリア−西ドイツ
後半11分、イタリアの先制ゴール
前半0−0、後半11分、西ドイツ側の反則で、イタリアはドイツ陣25メートルでFK。ドイツ側がまだ守備体制に入らない内に、右サイドへ、ジェンチーレが上がって来た。それを見て、タルデリがFKを右へ振る。ノーマークのジェンチーレは、右サイドから、まるでここからFKとでもいうように狙って、ゴール前へライナークロスを送った。これに合わせて飛び込んだのが左DFのカブリーニ、バウンドしたボールにカブリーニは合わなかったが、その左側にパオロ・ロッシがいた。姿勢を低くし、頭に当てたボールは、ゴール左へ。
1982年ワールドカップでイタリア優勝の立役者となったパオロ・ロッシ(1メートル78、76キロ)については皆さんもまだ記憶に新しいハズだ。私には、1978年のワールドカップと今度のワールドカップしか見るチャンスのなかったプレーヤー(出場停止処分のため1980年欧州選手権も、コパデオロも出ていないから)で、彼のオリジナルがどこにあるかは、はっきりしていない。ただし、はっきりしているのは、ゴール前の、相手の一番イヤなところへ、入り込んで、ボールを受けることの上手いこと。そして、攻撃開始のときに絡むドリブルの方向のいいこと。
82年のワールドカップ2次リーグでブラジルから奪った3得点は、一つは、左からのクロスをファーポストでヘディングし、一つは、相手バックスの横パスをかっさらってのシュート。もう一つはCKの後の味方のシュートをゴールマウスで足に当てたものだった。
頑健型でなく、スリムで、早さを基調とするロッシは、78年ワールドカップの19歳の頃に、すでに、“速”の中に“遅”、急のなかに緩を織り込むことを知っていた。プロフェッショナルともなれば、まず「急」がなければならぬが、急だけで相手を困惑させる力がある若い内に、緩を身に付けるのも一つの大きな才能だ。
緩と急の他に、ロッシは、もう一つ相手の守りのイヤな地域に気付かれずに侵入する才能を持っている。
日本ではベルリン・オリンピック(1936年)以来、長くシュートの名人と言われた川本泰三さんが、“消える”名人であった。相手の視野から消え、ゴール前の危険地帯に気付かれずに入って来る訳だが、ロッシもこの“消える”要領を知っているようだ。私の記憶では62年ワールドカップのソ連のCFワレンチン・イワノフとも似たところがある。
王様ペレが日本で見せたスーパーゴール、そして、皆さんもテレビでご存知の74年、78年、82年ワールドカップ決勝の得点シーンを思い出し、そのゴールスコアラーとなったストライカーの個性を比べてみた。
次項から、日本が生んだ釜本邦茂選手(現・ヤンマー監督)の幾つかのゴールシーンを再現し、そのときにどのような技術や、戦術が必要だったかを勉強したいと思う。
(サッカーマガジン 1983年11月1日号)
